妻籠宿と奈良井宿
妻籠宿は近くの有料駐車場から歩いてすぐのところに橋があり渡ることができました。
妻籠宿と本陣、脇本陣
妻籠宿は中山道と飯田街道の追分に位置する交通の要衝であった。天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、妻籠宿の宿内家数は31軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠31軒で宿内人口は418人であった。1960年代に深刻となった長野県の過疎問題の対策として、開発事業としての保存事業が基本方針となった。1968年から1970年にかけて明治百年記念事業の一環として寺下地区の26戸が解体修復された。その後、観光客が増え始めたことから観光関連施設の整備が行われるようになり、保存事業を制度面から後押しするために、1973年に当時としては例の少ない、町独自の町並み保存条例である『妻籠宿保存条例』が制定された(1976年に『妻籠宿保存地区保存条例』へ改正)。
経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、いち早く地域を挙げて景観保全活動に取り組んだことが評価され、1976年、国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれた。他の保存地区と異なり、周辺の農地など宿場を支えた環境全体を保存するため、国有林を含めた広範囲が選定されている。(ウイキペディアより)



歩く人は右側の木の橋を渡ります。



妻籠宿の建物の特徴として屋根が石置きになっていて、木の上に石を置いています。これは瓦が手に入らなかったことが考えられるそうです。また、屋根が低く2階には荷物を入れる程度にするようにお達しがあったとのことで、これは本陣、脇本陣より高くすることができなかったそうです。
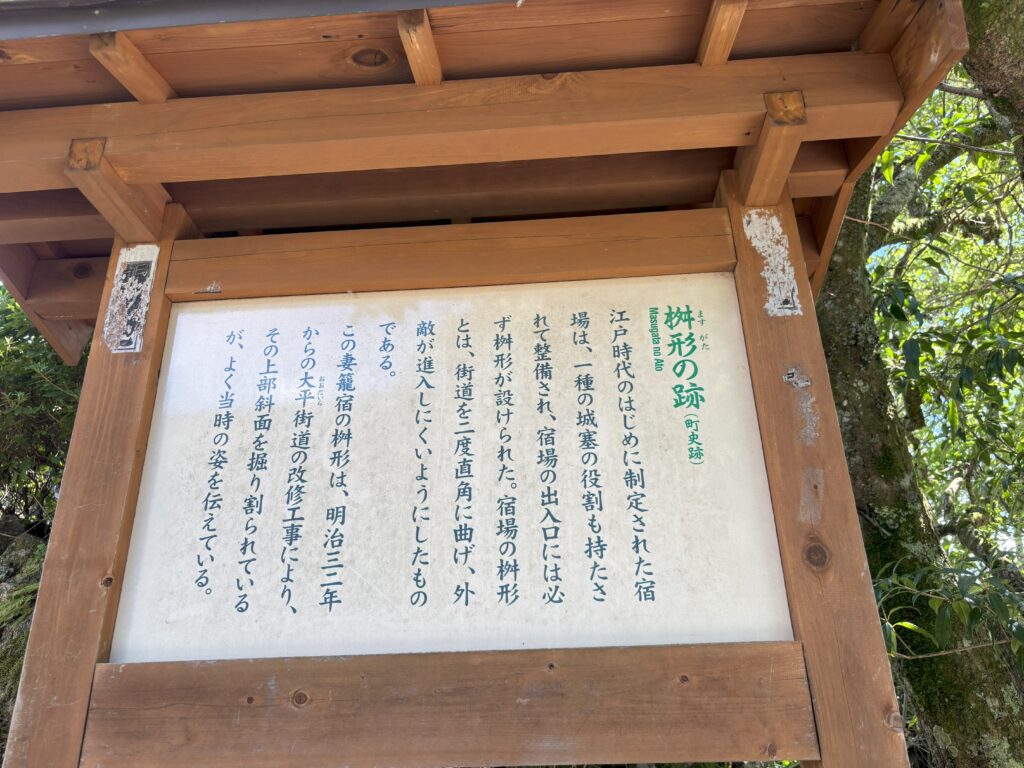



馬籠宿は何回かの大火でほとんど昔の家屋が残っていないため復元されていましたが、妻籠目は昔の家屋が残っており道の細さや家屋の状況などわかって風情を感じました。





明治天皇が寄られた時の部屋で、この部屋は誰も使用しなかったそうです。


家を守るため毎日炭を焚いて燻しているそうで屋根からの灯がとても美しかったです。

そのあと本陣も見学しました。
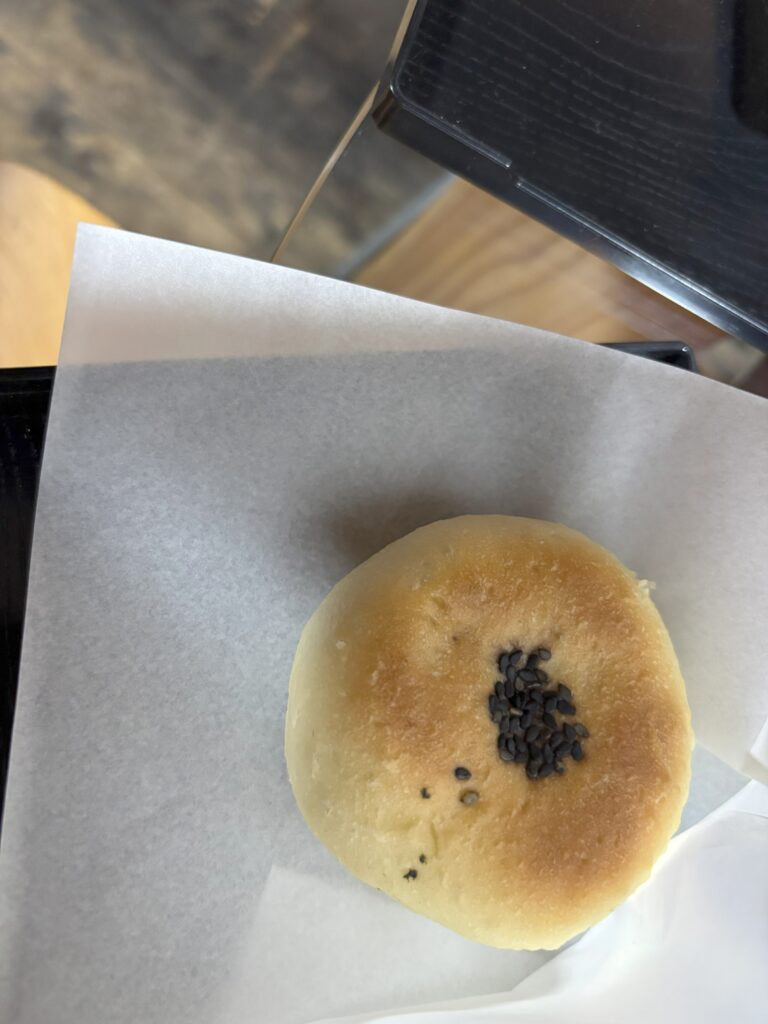


暑かったので途中で飲み物頂きました。疲れてたので美味しかったです。
おやきは野沢菜食べましたが地元では食べられないので美味しかったです。
奈良井宿
塩尻市(旧楢川村)の奈良井川上流に位置する、標高900m台の河岸段丘下位面に発達した集落である。現在は重要伝統的建造物群保存地区として、繁栄した当時の町並みが保存されている。山あいに寺社を擁し、宿場、蕎麦などの食事処、土産物店など、観光できる街並みに整備されている。木曽路十一宿の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高い。難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」といわれた。江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、中町と上町の間に鍵の手がある。(ウイキペディアより)







お昼にうどんを食べたが、黒麦という変わった小麦を使用しており、お蕎麦のようでした。
ニャンズ






