座敷わらし伝説の温泉郷 金田一温泉
江戸時代の寛永年間3年(1626年)に発見され、古い歴史を誇る金田一温泉。起源については1000年以上も前に蝦夷の酋長アテルイが湯浴みしたのが始まりとの説や、開湯年代を探るのはの難しいが、金田一の地名の由来について、南部氏の祖光行の第4子の四戸氏から出た金田一氏に因む説や、アイヌ語で山の方にある川(または沢)とする説など。古くから南部藩の指定湯治場(侍の湯)だったが、以前は湯田温泉と呼ばれ、田んぼから湯が湧いていたから湯田という名がつけられた。金田一温泉には12の源泉があり、岩手県内で唯一のラジウム泉で、神経痛や皮膚病に効能があり、身体の芯まで温まる。また座敷わらし伝説や、金田一京助、三浦哲郎ゆかりの宿があり、年間約30万人が訪れている。温泉の泉質は単純温泉(低張性弱アルカリ性低温泉)。温泉の効能hさ神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進など。泉温は約33.8度。湧出量は毎分約364リットル。


まず初めに観光案内所に行こうと思ったのですが、この日はお休みでした。残念です。しかし、たまたま旅行中の秋田から来たご夫婦と色々話ができて楽しかったです。
緑風荘に伝わる座敷わらしの伝説
およそ670年くらい前の南北朝時代。
当家の先祖である藤原朝臣藤房(万里小路藤房)は、南朝の後醍醐天皇に仕えていました。
しかし、南北朝戦争において南朝は敗北し、北朝の足利軍に追われ現在の東京都あきる野市に身を隠しました。
その後、さらに北上を続け、現在の岩手県二戸市にたどり着きました。 道中、二人連れていた子供の内、当時6歳だった兄の亀麿が病で倒れ幼き生涯を閉じました。 その際『末代まで家を守り続ける』と言って息を引き取ったそうです。
その後、守り神<座敷わらし>として奥座敷の槐(えんじゅ)の間に 現れるようになったと言い伝えられています。
その姿を見たり、不思議な体験をした人は大変な幸運(男=出世 女=玉の輿)に恵まれると伝えられ、実際座敷わらしに出会った人には必ず良い事があったそうです。
またひとたび座敷わらしに気に入られると、どこであろうと座敷わらしが会いに来てくれるそうです。
座敷わらしとして現れる「亀麿」は昔から多くの著名人も目撃し、 また、現在も多くの宿泊者に不思議な現象を起こし沢山の体験談で語り継がれております。




庭に歌碑がありとても手入れの行き届いたお庭でした。



いまだに色々と不思議な体験ができる座敷わらしが出ると言われている「槐(えんじゅ)の間です。とてもきれいなお部屋でした。

「槐の間」の隣のお部屋です。こちらのほうが趣がある感じでした。
お風呂はPH8.0で少しトロッとしたお湯でとても肌触りの良い温泉でした。



座敷わらしではないかと言われている6歳で亡くなった子供を祭っている亀麿神社です。緑風荘の裏にあって稲荷神社と並んで祭られていました。
本日の会計
| 品 名 | 代 金(円) | 雑 記 |
| ガソリン代 | 4,177 | |
| 食品 | 3,509 | |
| 酒たばこ | 8,970 | |
| 風呂 | 1,000 | |
| その他 | 22,922 | ナビ代わりにしていたタブレットが故障したので買いました |
| 計 | 40,578 | 新タブレット高かったです泣 |
本日のニャンズ


走行中リラックスして甘えるキキです。

ココは後ろ向きで知らん顔です。
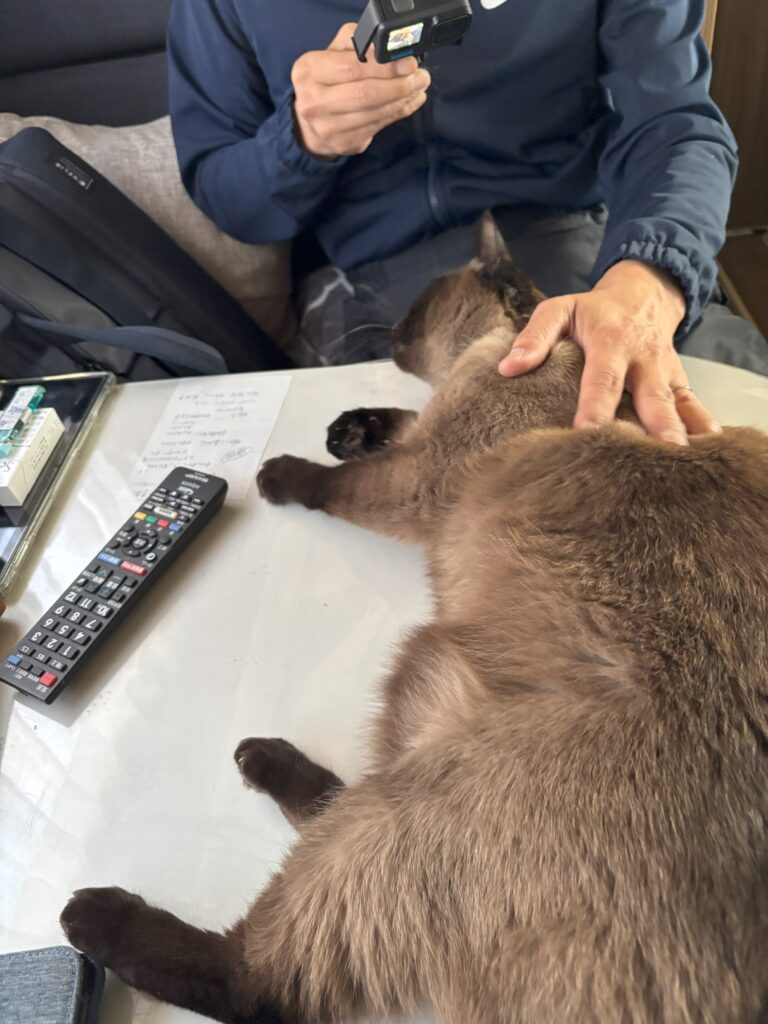
珍しく甘えるココ。

お澄ましのニャンズです。



